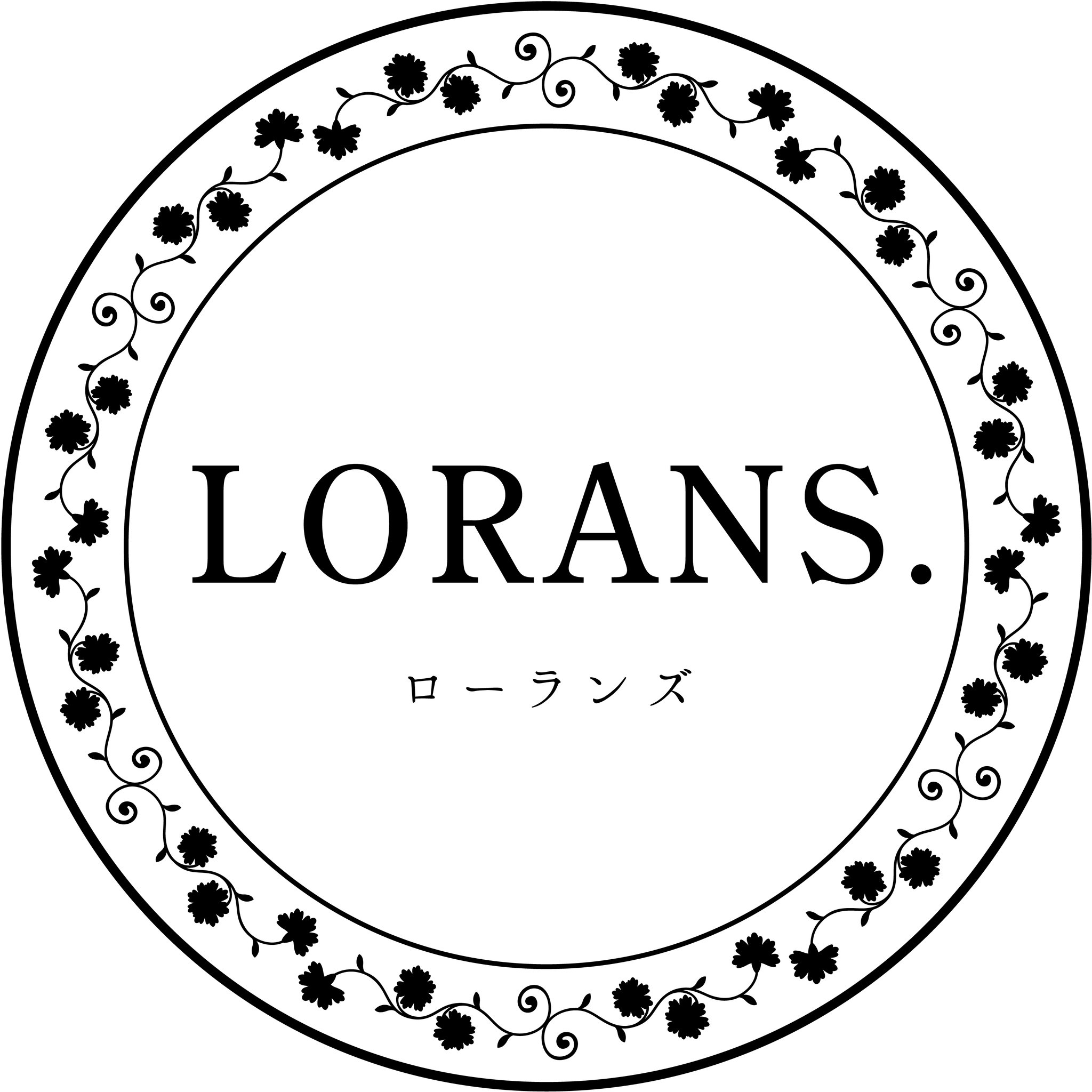障害があってもなくても、みんなが楽しめる場所を―『ちきゅうのにわ 幕張新都心店』に込めた想い

アルバイトを含めれば国内に6000人以上の従業員が在籍する株式会社イオンファンタジー。「モーリーファンタジー」「キッズーナ」「PALO」などさまざまなアミューズメント施設やプレイグラウンドを全国で運営し、子どもたちと触れ合いながら笑顔を生み出す会社です。2024年には「日本でいちばん会社にしたい会社」大賞で経済産業大臣賞を受賞し、社員を大切にする企業としても知られています。
今回は、2023年開業の東京ソラマチ1号店を皮切りに、25年8月には13箇所目となる幕張新都心店がオープンした『ちきゅうのにわ』にまつわるインタビューです。オープン記念の撮影イベントにカラフルモデルも参加し、夢中になれる楽しい時間を過ごしながら、素敵な写真を撮影していただきました。
会社を挙げてサステナビリティ活動に取り組む同社ですが、今回のインタビューを通して見えてきたのは、「活動を支えるのは、やはり個々人の想いである」ということでした。
=====
圓藤芙美さん
ショッピングセンター内「アミューズメント施設」と「プレイグラウンド」を運営する株式会社イオンファンタジーにて広報を担当。昨年、サステナビリティグループの責任者にも着任し、5つのプロジェクトチームをまとめている。各チームのメンバーは社内公募制で、障害を持つお客さま対応を担当するのは7名のメンバー+チームリーダーの計8名。生の声や専門家の意見に耳を傾けながら、ひとつひとつ真摯に進めている。
=====

誰もが楽しく遊べる場所に必要なのは「保護者へのサポート」
──「子どもと地球の未来を育む 遊んで学べるプレイグラウンド」というコンセプトを持つ『ちきゅうのにわ』。オープンの経緯を教えてください。
社会的な背景は2つあります。1つは、異常気象などさまざまな要因から外遊びがしにくい現代社会で、室内では動画ばかり見てしまう、体を使わせたいという親御さんの願いを叶えるためです。学びの形を強調することなく、自然を模した遊具で遊びながら地球という存在を知っていくきっかけを作れたら…という想いも込めています。
2つ目は、休日の遊び場の選択肢を増やすことです。とくに共働きの家庭は平日にお子さんと過ごす時間が取りにくいので、休日の過ごし方を大切にされる傾向があります。遠くの旅行もいいけれど、近くのイオンにある『ちきゅうのにわ』で、買い物ついでに遊んでいこうという選択をしていただけたら嬉しいなと思っています。
──家族向けの施設を多数運営される中で、障害のある子にはどのような対応を心がけておられますか?
ソフト面では「あったかタイム」というのを今年1月から試験的に設けています。障害のあるお子さまを持つ保護者から「周りの目が気になる」「ほかのお友だちとの関わり方が難しい」といった声が多く寄せられるので、周囲を気にせず遊べる時間帯を設定してみようと。
障害の有無に関わらずどなたでもご入場いただけるのですが、あったかタイムの主旨をお知らせして「お互いご配慮のうえでお入りください」と呼びかけています。
──子ども本人より保護者の方が、どうしても周りを気遣ってしまって…という面は多々ありますよね。試験的な試みとのことですが、今後も広げていけそうですか?
もっとご利用や反響があると思っていたのですが、蓋を開けてみたらそうでもなくて、「あったかタイムは本当にニーズがあるのかな」「誰のための試みなんだろう」と迷いが出ているというのが正直なところです。でも、チラシを握りしめて、その時間をめがけて来られた方もいらっしゃいました。
まだ1年経っていない試みですし、まずは多くの方に利用してもらい、実際の声を聞かせていただくことで、本当のニーズがどこにあるのかをさらに探っていけたらと思っています。
──『ちきゅうのにわ 幕張新都心店』では、障害児に配慮したインクルーシブ遊具だけでなく、初の試みもあるそうですね。
「光や音などが苦手な感覚過敏の人には、刺激を減らして落ち着けるスペースが必要」というアドバイスを専門家からいただき、カームダウンスペースを設けています。
元々目指していた「障害の有無に関わらず、すべてのお子さんが楽しめる施設」の象徴になるものを取り入れることで、「この施設は障害に対する理解がある。行きやすい場所なんだな」と、気軽に遊びに来ていただけたらという想いもありました。
──メディアでも取り上げられていますが、来場者の反応はいかがですか?
今のところ、こちらが想定していた方がお使いになるというより、大人の方が「へぇ、こんなものがあるんだ」と、中に入って体験されている感じです(笑)。でも、こういったスペースを必要とする方たちがいるという認識を持っていただけるだけでも十分意味はあるのではないかと思っています。

障害のある子もない子も笑顔で遊ぶ。その姿を見て気付いたこと
──今回、カラフルモデルのあおいちゃんとれんくんを起用していただいたのは、どういった想いからですか?
障害を持つお子さんも安心して遊べる場所だというのを多くの方にお伝えしたいという想いもありましたが、私自身が、障害のある子たちがちきゅうのにわで遊ぶ姿を間近で見たことがなかったので、どんな風に楽しんでくれるのかを知りたいと思ったからです。
撮影会にはカラフルモデルさんに加え、一般の招待客も含めて300人前後が集まり、そのうち約半分が弊社の従業員ファミリーでした。弊社従業員ファミリーも、カラフルモデルさんたちと一緒に遊んで欲しいと思っていました。
──撮影に立ち会われてみて、いかがでしたか?
あおいちゃんもれんくんも、他の子と同じようにすごく楽しそうに遊んでくれて、「障害がある子のためにこういう遊具を入れるべき」という区別とか、そういった発想自体がそもそも要らないのかもしれない、という気づきがありました。子どもたちは、障害がある・ないは関係なく、自分の遊びたい遊具があれば自分なりの方法で遊びます。なので、みんなが安全に楽しめるものを提供することが大切なんじゃないかなと。
実際に、車椅子のふたりが一緒にいても周りはとくに気にしていないように思えました。私から見ても、力いっぱい遊んでいる子どもたちのひとり、という印象でしたね。
──参加されたみなさんはどんな感想を持たれたのでしょうか?
アンケートでは、インクルーシブ遊具などに対して75%の人が「もっと導入していくべき」と肯定的に考えていました。「導入すべきではない」という感想もありましたが、これは否定的な意味ではなく、「特別扱いすべきではない」という捉え方だと思っています。
じつは以前、障害者割引を導入する際にも有識者から反対の声があったんです。「特別扱いすること自体がインクルーシブではない」と。様々な声を検討した結果、障害者割引は導入しましたが、先ほどのアンケート結果といい、障害に対する捉え方は本当に千差万別だなと感じました。
──必要なサポートや配慮さえあれば、子どもたちが「遊びにくさを感じる」ということはなく、むしろ保護者の「行きにくさ」を取り除いてあげることが大切なのかもしれませんね。
私たちのプロジェクトチームにも車椅子を利用している子のママがいて、「何より気になるのはわが子を見る周りの目です」など、当事者の気持ちを話してくれます。障害に対する理解が進んでいない世の中と、それに悩む当事者がいて、そこに子どもの遊びにくさが生じているのかなと思います。
先ほどお話しした「あったかタイム」も、行き着くところは貸し切りだと思っているんです。でも、まだ反響の薄い現状では、企業としてなかなかそこまで持っていけないというところもあって…この後の進め方で迷うところもありますね。
──迷い…ありますよね。そんな中でも進めていくためには何が必要なのでしょう?
こういった課題を会社として進めていくには、担当者の熱意が必須だと感じています。弊社の場合、すでに最低限の必要な取り組みはしている状況なので、あったかタイムやカームダウンスペースといったプラスαの取り組みをしなかったとしても、店舗が困るということはありません。だからこそ、「それでも、このプロジェクトをやるんだ」という熱意を持って臨めるかが重要なのかなと思います。

空間や設備を整える以上に、「関わり方」が大切なのかもしれない
──圓藤さんご自身は、どんなことをしていきたいと思っていますか?
弊社はイオングループなので、たとえば「イオンシネマで映画を観て、プレイグラウンドで遊んで、レストランでゆっくり食べて」という風に、障害のあるお子さんも保護者の方も気兼ねなくマイペースにイオンの中で一日を過ごしていただけるようなイベントなども思い描いていました。でも、その前にまだまだやるべきことがあるのかなと感じています。
──具体的には何を解消すればもっと取り組みが進むのでしょうか?
まずは、ニーズをしっかり探ること。ニーズがあって、誰かに求められているからこそ頑張れる!と思いますし、会社という大きな存在を動かすには、実際どんな需要がどのくらいあるのかを数字などで示す必要があります。
以前、イオンシネマを提供しているイオンエンターテイメント株式会社と弊社とで、「あったかタイムinイオンシネマ」という、発達障害・知的障害児のための貸し切り映画鑑賞イベントを開催しました。そのときは多数の応募があり、大成功だったんです。
障害のある子のためのエンターテイメントにニーズがあることは間違いないので、今後は「そのニーズが具体的にどんなものなのか、それに対してどう反応すればいいのか」をより深掘りしていけたらと思っています。
──「あったかタイムinイオンシネマ」ですか!それは確かに楽しそうなイベントですね。
そのとき参加してくれた発達障害・知的障害児の保護者へのアンケートで「イオンモールで困っていることはありますか」と質問したところ、「フードコートでなかなか席が取れない」というのが一番多くて。健常児の親御さんと同じ困り事なので、私たちメンバーとしては「逆に言うと、イオンモールを利用する際に、障害があるという理由で困っていることは他にないということ?それは、いいことだよね?」と。シネマに対しては「映画を観る」ことへの普段のハードルが高いからこそ、イベントの反響も大きかったんじゃないかな、と考えたりもしました。
──それは、御社がこれまで小さな取り組みを重ねてきたからこそ、「イオンモールでは困らない」という結果になっている可能性もありますよね?
弊社だけでなくイオングループ全体での取り組みがそのような結果になっているのだとしたらとても良いことだと思います。弊社のプレイグラウンドでも「うちの子は自閉症なんですが、入ってもいいですか」と事前にスタッフにお尋ねいただくことがあって。その場合は「もちろんです、どうぞ!」とお迎えしますが、何も尋ねずに普通に入場して楽しんでくださっている方も確かに多いかもしれません。お子さまと保護者さまにとって気兼ねなくご利用しやすい場所になっているのであれば嬉しいです。
──ハード・ソフト両面からの工夫はもちろん大きいですが、その場で交流するスタッフの方がどう対応してくださるか、笑顔で歓迎してくれたか、困ったときにどんな声をかけてくれたか…そういったことのほうが保護者の心に残るかもしれませんね。
本当にそうだと思います。私たちのプロジェクトで「今年やろう」と掲げている目標が5つあって、その1つが社内教育なんです。プロジェクトメンバーの中でも「社内教育が何より大事」と考えています。たとえば「あったかタイム」をいくら整えても、そこで関わる店頭のスタッフの不用意なひと言があったらとしたら全部くずれちゃうこともあり得るよね、と。障害児理解の深いメンバーの声を聞きながら進められるのはありがたいなといつも思います。

管理職もスタッフも、一丸となって臨む「真のインクルーシブ」
──社内教育として、たとえばどんなことを実施されていますか?
まず、社長、取締役をはじめ、全国の店長やエリアマネジャー、本部の全社員などが勢揃いする年に1回の全社会議の中で、有識者を招き発達障害をテーマにした講演会を行いました。
発達障害の講演にしたのは、障害のあるお子さんへの取り組みを進めるには社内の理解が大事だと私自身が痛感しているからなのですが、これをきっかけに、関心を持つ人、深めた人はかなり増えたと思います。
──まずは管理職の方たちの認識が変わって、現場にも広がっていくイメージでしょうか。
そうですね。さらに、7月には店舗スタッフでも参加できる社内セミナーを開催しました。どのくらい参加してくれるかな?と思っていましたが、全国から100人近く参加してくれました。その他にも、社内報で発達障害に関する特集を組んだ際、「障害のあるお客さま対応で困ったことはありますか」と従業員に投げかけたところ、質問も200以上。その中から代表的なものを20ほど選んで有識者に答えてもらいました。
──どんな質問があったんですか?
多動のお子さまでおもちゃを投げてしまう場合はどう対応すればいいか?というような内容には、投げてしまう目的は2つあって、投げることを楽しんでいる場合と注意を惹きたい場合があります、と。それぞれの対応方も具体的に教えていただきました。
社内報の反響も大きくて、読者アンケートでは「よかったページ」の上位に挙がり、関心の高さを改めて感じましたね。
──ほかにも社内教育として何か実践されていますか?
弊社ではさまざまなスキルの認定制度を設けていまして、その中にお客さまへの対応が上手な人を認定するCSインストラクターというのがあります。その認定セミナーの中に、障害のあるお客さまへの対応事例を今年から追加しました。受講者は年間400人ほどになります。
──個々の想いが積み重なって、運営施設全体への安心感につながっていくのでしょうね。
アルバイトさんも多い会社なので、人員の入れ替わりも頻繁です。なので、「セミナーを1回やりました」「今年はこういうイベントをやりました」では意味がなくて、毎年続けることが大事だと思っています。
私自身は広報の部署にいますので、PR戦略とか、子どもたちと取り組むSDGsイベントとか、いろいろな企画案も提案いただきます。でも、1回やったら終わりという、いわば話題作りのための取り組みは個人的にやりたくないと思っていて。たとえば「何か取り組みを行いました、新聞に載りました、これが成果です」というだけで満足するのは、ポリシーに反するんです。大事なのはそこじゃない、みたいな(笑)。
──真摯に取り組まれているからこそ、先ほどおっしゃっていたような迷いも出てくるんでしょうね。ちなみに、プロジェクトチームとしてやりたい5つのうちの1つが社員教育でしたが、残り4つは?
ハード面としてカームダウンスペースとインクルーシブ遊具を導入する、ソフト面であったかタイムを常設化する、あとはイオングループとして推進しているパラスポーツ「ボッチャ」イベントを実施することです。
そして、5つ目としてぜひおすすめしたいことがあります。アミューズメント施設の中に「よくばりパス」というのがあって、これはカードにチャージすると30分、もしくは60分間、体感ゲームや乗り物が遊び放題になるものです。たとえば1回100円のメリーゴーランドの乗り物に乗ってすぐに「やっぱりやーめた」「あっちのほうがいい!」と子どもの気が変わると、「せっかく100円を入れたのに無駄になった!」となるのですが、よくばりパスは遊び放題なので、気にせず次の遊びに移れるんです。
有識者から「発達障害の子は、おしまいに抵抗があって、気持ちの切り替えがしにくい特性を持つ子も多いので、遊びの終わりがわかりやすくなると良い」というアドバイスがありました。「30分遊び放題」と、終わりの時間があらかじめシステム化されている「よくばりパス」は、そういう意味で相性のいいサービスだと思います。年齢制限もないので、使っていただきやすいのではないでしょうか。
──最後に、プロジェクトを推進する圓藤さんの想いを改めて教えてください。
取り組みを始めた当初、「お子さんの障害を気にして外出をあきらめている保護者って多いんだよ」という話を聞きました。周りの視線を気にして親御さん自身が制限をかけてしまうことも多いと。それで、もっと気兼ねなく行きやすい場所や機会をうちの会社で提供することはできないだろうか、というのが私の中でのスタートだったんです。
あったかタイムも、カームダウンスペースもインクルーシブ遊具も、そしてスタッフの対応も、いろいろとやっていく中で、遊びに連れて行きたい気持ちをあきらめていたご家族にサービスが届いて、誰かひとりでも「また出かけよう」「楽しもう」に繋がったら嬉しいなと思います。
まだまだ歩みは遅くて迷いや悩みもありますが、その気持ちを大切に、進んでいきたいと思います。またカラフルモデルさんたちとご一緒できる機会があれば、さらに嬉しいですね!
取材・文/木戸上かおり
=== 内木美樹より一言 ===
私自身も重度障害児の親ですが、感じるのは「障害のある子でも、イオングループさんの施設には連れて行きやすい」ということです。
以前、弊社が運営している「チーム☆チャレンジ」という、障害児者の保護者向けのオンラインコミュニティ内でアンケート調査を行った際、「(子供に障害があることで)子連れでの観覧が難しいと思う事がありますか?(ありましたか?)」という質問に対して約8割の方が「ある(たまにある)」と回答しました。
そして、「映画館にどのような配慮をしていただける事で、難しさは軽減されると思いますか?」という質問には、
1位 歩き回れる、声を出せる映画(47票)
2位 障害者デー(24票)※障害者専用のスクリーン
という声が挙がり、こちらはまさしく、イオンシネマさんがやられている「あったかタイム」そのものです。このように障害者やその家族に目を向けてくださったこと、私たちの困りごとを知った上で導入を決断してくださったこと、大変感激しています。
そして、この度のカラフルモデルの起用。れん君やあおいちゃんの写真を見る事で、障害児を育てている別の保護者は「うちの子も『ちきゅうのにわ』に行っていいんだ」と思い、障害児を育てていない方も「障害児にもやさしいって素敵だな」と思ってくれるでしょう。
このように、イオンファンタジーさんが発されたやさしさが1人また1人と伝わり、社会が「違い」を排除するのではなく受容するようになれば、誰もが住みやすい世の中になると信じています。
その大きな一歩を進めてくださったイオンファンタジー様、責任者の圓藤様には感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。